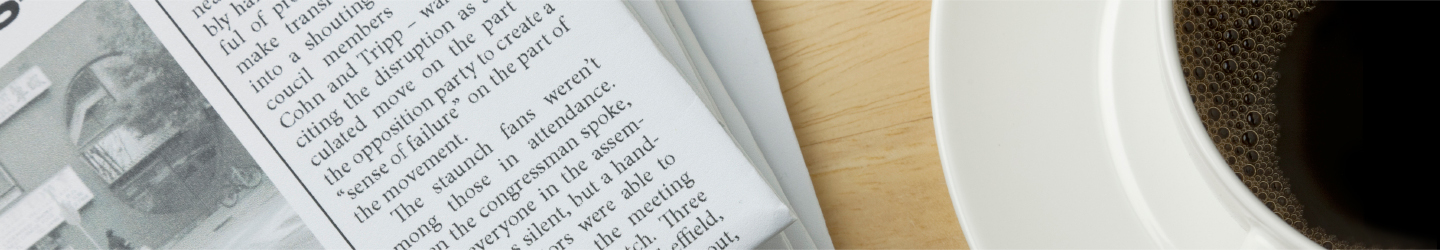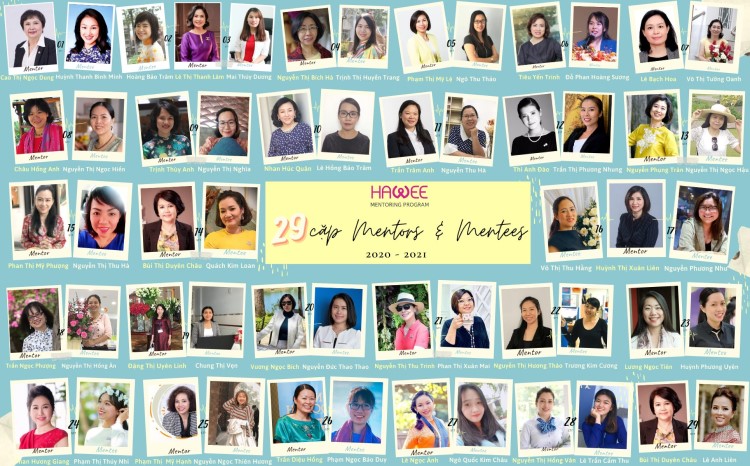効率に関する考え
ベトナム効率院によると、効率とはインプット要素(労働、資金、原材料、エネルギーなど)からアウトプット(数量、付加価値)を作り出す効果を測定する基準で、以下の公式で表示されます。
1958年から、ヨーロッパ効率機関(EPA)が効率を次のように定義しました:「効率が思考形態の一つで、存在しているものを改善するために連続的に努力する態度である。今日の人間は昨日より良く仕事ができる-明日は今日より良くなるはずである。そして、結果はどのようになっても、改善意志の方が大切である;それは変わってきた条件に適応する能力であり、新技術、新方法を適用するた目の連続的努力である;人類の新法に対する信条である」。この定義は現在多くの国に使用されています。
企業の効率を分析して評価するために、以下の2グループの効率指標システムを使用しています:
1/それぞれぞれのインプット要素(Factor Productivity)によって計算される効率、計算方法:アウトプット/1つのインプット要素。例えば:労働効率=アウトプット/労働数。これらの指標はそれぞれのインプット要素の効果を分析するためです。
2/インプット要素(Total Factor Productivity)によって計算される効率、総合要素効率(TFP)とも言われています。この指標は労働品質、先進的技術応用、管理程度アップなどの要素の作動によって作り出された効果を表示します。
べとナウ労働者の労働効率が6億人数の人口であるアセアン経済共同体(AEC)の各国と比べてより低いという問題を解決するために、企業模型に適当な効率計測指標を選ぶと共に、もう一つ重要な要素は労働効率が大きく改善されない場合、人一人一人の労働者及び企業に悪い影響を与える物質(定量)、感情(定性)の損失とリスク(予想)の見方を正しく確立することです。
企業と労働者は限界と支障を超えるたえに、何を考えて、する予定ですか?問題を正しく理解することや自分や企業や国の権利をどうすれば守れるのかということに止まりません。もっと重要なのは思考から変更すべきです。
問題を梢から解決して(外形の兆しに基づく)低い効率の問題を間違えて診断すれば(中の元凶)変えたい問題を改善することができません。お互いの利益を責任、規律を持って協力する精神で調整して、共有の目標を向って、効率を造り出して、仕事と生活のバランスをとるのが21世紀の人間のやむを得ない傾向です。
NHQ
TAG: